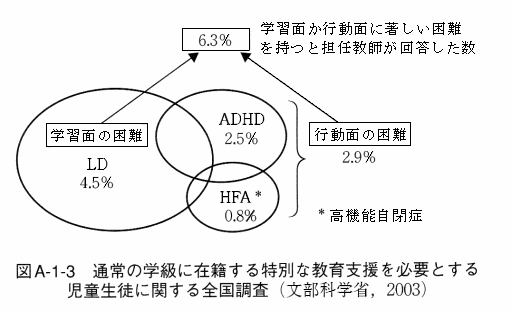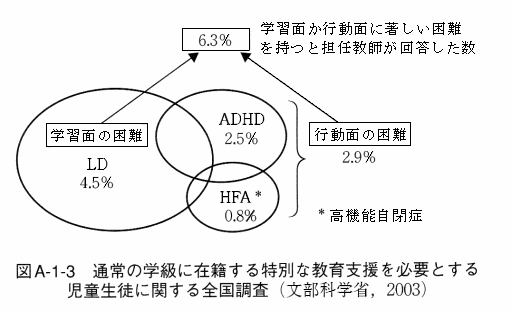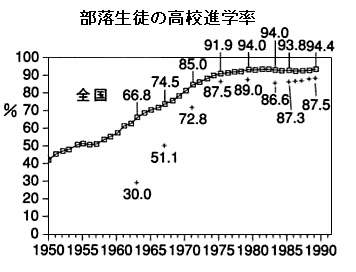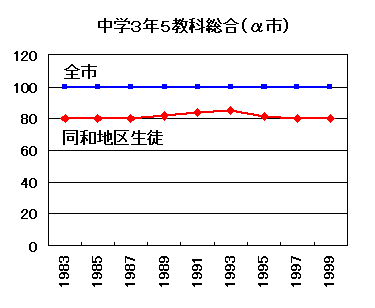◆200807KHK234A1L0366AE
TITLE: 特別支援教育は「排除」か「包摂」か?
AUTHOR: 原田 琢也
SOURCE: 大阪教法研ニュース 第234号(2008年7月)
WORDS: 全40字×366行
特別支援教育は「排除」か「包摂」か?
原 田 琢 也
1 特別支援教育はインクルージョンへ向かっているか?
2007年4月より特別支援教育が本格実施された。特別支援教育とは,2003年3月に出された「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(以下,「最終報告」と略記)によれば,「これまでの特殊教育の対象の障害だけではなく,その対象でなかったLD,ADHD,高機能自閉症も含めて障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し,当該生徒の持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するために,適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである」(下線は筆者)。
特別支援教育は,一般的にノーマライゼーションやインクルージョンといった近年の障害をめぐる潮流に合致したものだととらえられている。たとえば,2004年1月に文部科学省から出された「小中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」(以下,「ガイドライン」と略記)は,上記の定義を引用した直後に,「このように『特別支援教育』は,児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行うものです」と述べている。また平成2007年に文科省から出された「特別支援教育の推進について(通知)」も,「さらに,特別支援教育は,障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず,障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり,我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている」と述べ,特別支援教育が障害を持つ子どもの教育的ニーズに応えるためだけのものではなく,ノーマライゼーションやインクルージョンといった近年の障害をめぐる潮流に合致したものであることを強調している。特別支援教育士資格認定協会(2007)の『特別支援教育の理論と実践Ⅰ-概論・アセスメント』においても,ノーマライゼーションやインクルージョンが,障害をめぐる世界の動向であることを確認した上で,「特別支援教育の推進も,近年におけるこのような国内外の障害のある人の捉え方や対応の基本方針を踏まえて取り組まれている」と説明されている。
インクルージョンとは,ピーター・ミットラー(Peter Mittler)によれば,「すべての学校を,遥かに多様な子どもたちのニーズ-障害のある子どもたちだけでなく,貧困によって,性によって,なかでも個性の成長や人格の発達を犠牲にして教科の成績を優先するカリキュラムによって,軽視され,除外されているすべての子どもたちのニーズに応えられるように改革し,再構築することであるという考え方」と定義される。また,山口薫は従来の統合教育との違いを強調する文脈の中で,「統合教育と決定的に違う点は,子どもをまず障害のない子どもとある子どもに分けた上でその統合を進めようとする統合教育に対し,インクルージョンでは,子どもは一人ひとりユニークな存在であり,一人ひとり違うのが当たり前であることを前提として,すべての子どもを包み込む教育システム(education for all)の中で,一人ひとりの特別なニーズに応じた教育援助を考えることにある」と説明している。
特別支援教育は,たしかにLD,ADHD,高機能自閉症など,いわゆる発達障害を持つ子どもに対して,今まで以上に手厚く,ていねいに一人ひとりのニーズに応じた支援を行おうとする点で,一見インクルージョン教育の理念に合致しているように見える。しかし,特別支援教育では,上述のように,対象を「障害のある児童生徒」と限定し,「障害者/健常者」といった線引きを堅持し,そのラインを今まで「健常者」とされていた領域にずらすことによって,障害者の数を増やすことに帰結する。たとえそれが支援の方法を明らかにする一助になるのだとはいえ,子どもを特別支援教育の対象とするためには,一旦は何らかの「障害」にカテゴライズすることを避けて通ることはできない。そう意味では,日本の特別支援教育の考え方は,むしろインクルージョン教育の流れに逆行しているものと言わざるをえない。
2 「6.3%」という数字の意味
先日,竹田契一氏の講演を聞く機会があった。氏は,日本LD学会理事であり,また特別支援教育士資格認定協会の会長でもある。いわばこの道の第一人者だ。氏は講演会で,次のように力説されていた。「LD,ADHD,高機能自閉症など,特別支援教育の対象児童生徒は全体の6.3%いるはずであり,まだ特別支援教育の対象として10名ぐらいの児童生徒の名前しかあがっていない学校は,特別支援教育に関する認識が不足している。もっとしっかり精査して,より多くの発達障害を持つ児童生徒を早期に抽出すべきだ」。私は耳を疑った。
この6.3%という数字は,特別支援教育関連の書物や研修会では,LD,ADHD,高機能自閉症の割合を示すものとして,必ずといっていいほど用いられる数字である。しかし,この数字のルーツを遡っていけば,この数字に根拠がないことがわかる。この数字は,文部科学省が2002年に実施した,「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」に依っている。この調査は,全国から抽出された370校,4328学級の担任が,児童生徒の学習や行動に関する質問に応えるという質問紙調査の方法で行われた。その結果,「学習か行動面で著しい困難を示す」と判断された児童生徒の数が,全体の6.3%だったというにすぎないのだ。
その調査には,「留意事項」として次のような断り書きがついている。「本調査は,担任教師による回答に基づくもので,LDの専門家チームによる判断ではなく,医師による診断によるものでもない。従って,本調査の結果は,LD,ADHD,高機能自閉症の割合を示すものではないことに注意する必要がある」。
ところが,文部科学省の『ガイドライン』においては,この数字が次のように扱われることになる。「LD,ADHD,高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒について,平成14年文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」(別添)の結果は,その調査の方法が医師等の診断を経たものではないので,直ちにこれらの障害と判断することはできないものの,約6%程度の割合で通常の学級に在籍している可能性を示している」(『ガイドライン』p.123)。さらにその数頁後では,「LD,ADHD,高機能自閉症により,学習面や生活面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒数は,既に述べたとおり,通常の学級に在籍する児童生徒の6%程度と考えられること」(『ガイドライン』p.135)。調査時点においては,6.3%という調査結果は,「LD,ADHD,高機能自閉症の割合を示すものではない」と明言していたにもかかわらず,2年後に出された「ガイドライン」においては,それがまるで通常の学級に在籍するLD,ADHD,高機能自閉症の児童生徒数の割合を示すものであるかのように扱われているのである。
竹田氏が会長を務める特別支援教育士資格認定協会の『特別支援教育の理論と実際』においては,さらに遠慮がない。「文部科学省は通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査(文部科学省,2003)を実施した。この調査は専門的な診断による出現率調査ではないが,少なくとも小・中学校における通常の学級の担任教師が,LD・ADHD・高機能自閉症の典型的行動特徴を示す児童生徒をどの程度把握しているかという調査である。調査によれば,LDの疑いのある学習面の困難を示すもの4.5%,ADHDの疑いのあるもの2.5%で高機能自閉症の疑いのあるもの0.8%,これら行動面の困難を示すものは2.9%,そして学習面か行動面のどちらか,あるいはどちらにも著しい困難をもつと担任教師が回答した数は6.3%であった」。ここでは「特別な教育的支援を必要とする児童生徒」は,即ち「LD・ADHD・高機能自閉症の典型的行動特徴を示す児童生徒」というように言い換えられている。そしてその説明の横には,図1のような概念図が添えられている。
この一連の操作は,次のような二つの命題を安易に三段論法で結びつけることによって作り上げられている。①「LD,ADHD,高機能自閉症の子どもは,学習か行動面で著しい困難を示すものである」。②「通常の学級において,学習か行動面で著しい困難を示す児童生徒は6.3%いる」。よって,③「通常の学級にはLD,ADHD,高機能自閉症の子どもが6.3%いる」。①の命題は「真」であり,②の命題も,調査方法と解釈には疑問は残るが,一応「真」と言える。しかし,③は「真」ではない。通常の学級において学習や行動面で著しい困難を示す児童生徒は,LD,ADHD,高機能自閉症の子どもばかりではない。
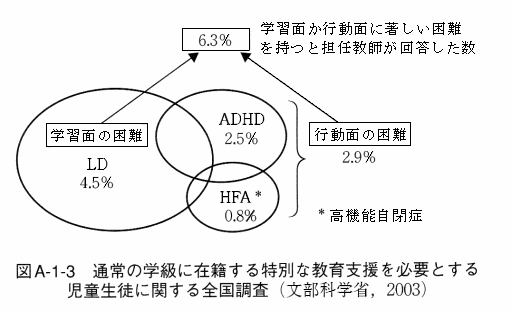
図1 通常の学級に在籍する特別な教育支援を必要とする児童生徒
に関する全国調査 特別支援教育士資格認定協会編(2007)
3 「学習や行動の課題」は社会的につくられる
私は教師になってからの約20年間,校区に「同和地区」を含む学校に勤務し,同和地区生徒の学力向上に取り組んできた。同和地区の子どもたちの学力問題は,同和教育の領域だけではなく,日本の教育全体においても,大きな教育課題の一つであり続けてきた。
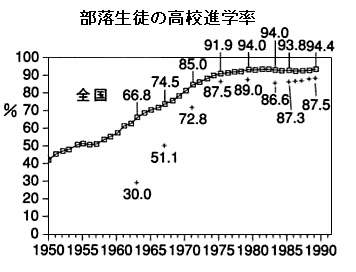
図2 高校進学率の推移 鍋島(1997)
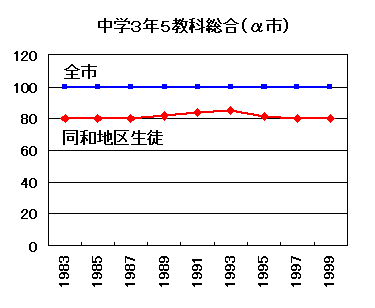
図3 中学3年5教科の推移 外川(2002)
図2は高校進学率について,全国と同和地区を比較したものであるが,1963年には全体の高校進学率が66.8%であるのに対して,同和地区の高校進学率は30.0%と,全体の半分にも満たない状況である。またこの時期には,同和地区の子どもたちの「非行」が問題にされている。その原因として,多くの同和地区生徒にとってはまだ学校に行くことが関の山であり,授業についていくことは難しく,進路展望が持てない状況にあったこと,にもかかわらず,学校・教師が子どもたちのおかれているそのような状況を十分に理解せず,適切に対処することができないでいたことが考えられる。子どもたちの反学校的な行動は,そのような学校体制に対する異議申し立ての意味を持っていた。
その後,同和地区解放奨学金や同和加配教員といった制度面の整備に加え,全国各地で展開された進路保障・学力保障の取り組みによって,同和地区の高校進学率は短期間に飛躍的に上昇することになる。しかし,それ以降,若干の上がり下がりを繰り返しながらも,5%前後の差は縮まらず現在に至っている。
図2では,1983年から2000年までの同和地区生徒と同和地区外生徒の5教科総合の得点の推移が比較できる。ここ20年近く,同和地区生徒と地区外生徒の学力格差は全く縮まっていない。鍋島祥郎は,「同和地区の子どもたちの低学力傾向は戦後期を通じて一貫している」と主張し(鍋島1997),外川正明は,「高校進学率はほとんど格差のない状態になってきているにもかかわらず,実質的な学力についてはこの20年間で解消されていない」と結論づけている(外川2002)。さらに,志水宏吉(2002)は,1989年に行われた学力調査と,2001年に自らが行った学力調査の結果を比較して,「同和地区内外の学力の集団差は,明らかに拡大した」と,近年再び同和地区内外の学力格差が拡大していることを指摘している。
皮肉なことではあるが,この20年といえば,ちょうど筆者が教師になってからの期間と重なる。この間,校区に同和地区を含む学校では,同和地区の子どもたちの学力保障・進路保障を最優先課題として位置づけ,精力的な取り組みが続けられてきた。筆者自身も長年にわたり夜間の学習会の講師を務めてきたし,校内分掌の同和・人権教育部の一員として,学校全体の同和・人権教育の推進に努めてきた。この20年間,同和地区の子どもたちの学力・進路保障には計り知れないほどの多大な資本とエネルギーが投下されてきたことは事実である。にもかかわらずである。なぜ,学力格差はある一定のところから縮小しないのか。
このような問題関心に基づき,筆者は,同和地区内外の学力格差が形成されるメカニズムを解き明かそうと,研究に着手した。そしてその成果を昨年,『アイデンティティと学力に関する研究』(原田2007)として一冊の本にまとめることができた。この本を通して筆者が言いたかったことは,学力や学校における行動は社会的に構成されるということだ。そのメカニズムは実に複雑であり一言で説明することはできないが,思い切ってエッセンスだけを言ってしまえば,一つは,身体化された文化(社会学では「ハビトゥス」と呼ばれる)と学校文化のズレの問題。もう一つは,自らの社会的立場に対する意識(自己概念)の問題が,彼ら/彼女らの学力形成と学校における行動に大きな影響を及ぼしているということだ。
筆者はかつて,特別支援教育の対象としてリストアップされている子どもたちが,どのような社会的背景を持っているのか調べてみたことがある。するとそのリストに載っている子どもたちの中には,就学援助を受けている生徒,同和地区出身の生徒,外国につながる生徒,片親家庭の生徒が,全体におけるそれらの率より,相対的に高いことがわかった。この学校では,特別支援教育の対象をリストアップする際に,「LD,ADHD,高機能自閉症と思われる子ども」を抽出しているわけではなく,「学習や行動面で気になる子ども」を抽出しているのであるから,その中には社会的・経済的に厳しい状況にある子どもたちが多く含まれることは,当然の結果だと言える。先にも述べたように,生徒の学力や学校における行動は,社会背景の影響を強く受けているからだ。
ところが,日本の特別支援教育の定義では,通常の学級に通う生徒の中で特別支援教育の対象になるのは,LD,ADHD,高機能自閉症の子どもたち,つまり障害を持つ子どもに限られる。抽出する教員は,学校の日常において気がかりな子どもに対して,少しでも有意義な支援を届けたいという思いで,原因は特定できずとも,とりあえずその生徒をリストに掲載することになる。だが一旦リストに掲載されてしまうと,抽出者の意思とは無関係に,彼ら/彼女らにはLD,ADHD,高機能自閉症などの「障害者」として扱う「まなざし」が差し向けられることになる。社会的マイノリティの子どもや,経済的に厳しい状況にある子ども,あるいは虐待やDVなど家庭に問題を抱えている子どもに対して,社会や家庭の問題を不問にして,課題の責任を子ども個人の病理に求めていくことは,彼ら/彼女らの本当の意味での支援にならないばかりか,重大な人権侵害である。
4 「障害」は社会的につくられる
LD,ADHD,高機能自閉症はどのような「障害」なのだろうか。「ガイドライン」は,ごく簡単にではあるが,LD,ADHD,高機能自閉症の定義を載せている。LDの定義は次のようである。「学習障害とは,基本的には全般的な知的発達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すものである。学習障害は,その原因として,中枢神経に何らかの機能障害があると推定されるが,視覚障害,聴覚障害,知的障害,情緒障害などの障害や,環境的な要因が直接的な原因となるものではない」。ADHDの場合は,「ADHDとは,年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力,及び/又は衝動性,多動性を特徴とする行動の障害で,社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また,7歳以前に現れ,その状態が継続し,中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。」高機能自閉症の場合は,「高機能自閉症とは,3歳位までに現れ,他人との社会関係の形成の困難さ,言葉の発達の遅れ,興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち,知的障害の遅れを伴わないものをいう。また,中枢神経系に何らかの機能不全があると推定される」(すべて下線は筆者)。
いずれにせよ,原因を中枢神経の何らかの「機能障害」または「機能不全」に求めること,そしてそれが「推定」にすぎない点で共通している。しかし,高岡健は,「脳機能の障害というのは,一部の研究者が妄想的にそう思いこんでいるだけであって,脳に障害があるということを証明した人は,誰もいない」と言い切る。最近では,脳科学の進歩でかなり研究が進んではいるが,CTスキャンやMRIなどの脳機能イメージングでは脳の構造上の異常は一切検出されていない。ただボリュームメトリー(volumetory)というMRIを使った解析手法を用い,症状と関連の深い脳のある部位の容積を計測したところ,容積に違いがあることは判明している(榊原 2007)。
しかし,たとえ,脳の機能と症状との間に何らかの関係がある,という前提に立ったとしても,脳の機能に個人差があることは当たり前のことであり,その広がりはまるでグラデーションのように際限のない広がりを見せているはずである。たとえばある者は,側頭葉下部の紡錘回の機能が低く,人の顔を覚えることを苦手とするかもしれない。またある者は,前頭葉の容積が小さく,ワーキングメモリーの機能が低く,物事を順序立てて行ったり,同時並行で仕事をすることを苦手とするかもしれない。それらの違いは個性を作り出す一因にもなっており,違いがあることそのものに問題があるわけではない。しかしその広がりの中のどこかに,「障害/健常」を分かつ境界線が引かれ,その線より外側にいる者は「障害者」として位置づけられることになる。
だが,障害の有無を診断する際に,一人一人の脳の各部位の容積や機能が計測され,客観的な数値基準を基にして判断がなされるわけではない。実際には,発達検査やスクリーニングによって,学校生活や家庭生活における逸脱の度合いが計測され,教育的処遇に差異をつける根拠として,後から診断名が付され,中枢神経の機能障害と結びつけられていくのである。学習や行動における課題は,たしかに中枢神経の「機能障害」または「機能不全」と無関係ではないが,原因がすべてそこにあるというわけでもない。身体的要因から一人一人の違いは作り出されるが,その広がりの,ある部分に線引きをするのは社会の側である。そういう意味で,「障害」は社会的に構成される。
高岡健著『やさしい発達障害論』と石川憲彦・高岡健著『心の病いはこうしてつくられる』には,発達障害がいかに社会的につくられているかを裏付けるエピソードが数多く取り上げられている。その中よりいくつかをここに紹介することにする。
石川によれば,農業社会では身体障害者が問題視され,工業社会になると知的障害者が問題視された。そして情報産業社会の今日,「軽度発達障害」がトピックになり,政治的策動を通して今日の「特別支援教育」が生み出されたのだと指摘される。何が障害として問題視されるかは,社会状況によって変わるということだ。
情報産業社会への移行が進行したのは1980年代のことであるが,その頃,イギリスではアスペルガー症候群が,そしてアメリカでは高機能自閉症が発見されている。この点に関して高岡は次のように説明している。「1980年代は,新しいサービス・技術・専門産業の時代であり,かつての大量生産とは異なる,複雑な社会の到来を告げていました。このような複雑な時代に適応しにくい,一群の人たちがいました。それは,他者の裏をかいてサービスを売り込んだり,言葉巧みに自らをアピールすることができず,また臨機応変に振る舞うことが苦手な人々でした。一般人口の中から,彼らをアスペルガー症候群や高機能自閉症と名づけて,抽出していく根拠が,ここにあるわけです」。
また高岡は,篠原睦冶があるシンポジウムで取り上げた,1980年代のアメリカの学校の様子を紹介している。当時,その学校には,BDクラス,LDクラス,MRクラスなどのクラスが存在した。BDとは行動障害のことで,今日のADHDに相当する。MRは知的障害を意味する。LD学級には白人が圧倒的に多く,BDクラスには黒人が圧倒的に多かった。LDクラスは,白人中産階級の親たちが,自分たちの子どもをMRと差異化するために要求して作ってきたのだという。
アメリカとイギリスのADHDの発生率を比較したとき,かつてアメリカはイギリスの40倍だったことがあるそうだ。この点に関する高岡の説明は次のようだ。「アメリカでは,注意欠陥/多動性障害という診断名そのものや,メチルフェニデート(リタリン)という薬による,子どもたちへの管理が乱用されている現状があるからです。もっといえば,アメリカでは,スパニッシュやアフリカン/アメリカンなど,白人以外の人々が住むコミュニティの学校が,たいへん荒れているわけですが,その荒れている学校の責任を,注意欠陥/多動性障害という個人病理に,求めているのです。そして,それを薬物的に管理していくアメリカのやり方,つまり,学校の病理を子ども個人の責任に還元し管理していくやり方のために,100人に2人もの注意欠陥/多動性障害児がいると,いわれるようになったのです」。
日本でも,学級崩壊が取り沙汰されたすぐその後に,ADHD概念が普及し始めたことは,単なる偶然ではないと思われる。
5 「障害」とは何か?
障害は,一般的に,何らかの身体的損傷に起因して生じると考えられている。しかし,実際に人がそのことを「障害」と感じるか否かは,まわりの社会的環境に負うところが大きい。障害学では,前者の個人的側面を「インペアメント」と呼び,後者の社会的側面を「ディスアビリティ」と呼ぶ。医学はもともと,個人の身体的側面に関心を寄せる学問であり,医学モデルに依拠して現象をとらえようとする限り,社会的側面は自ずと視界の外に追いやられてしまう。先の事例に即して言えば,学習や行動における課題を,「中枢神経に何らかの機能障害があると推定される」LDなどの発達障害に直結させて考える姿勢は,障害を身体的な損傷(インペアメント)としてのみとらえようとする,医学モデル(個人モデル)に立脚した考え方である。医学モデルに依拠して障害をとらえる限り,社会的な問題は全て個人の身体的問題としてすり替えられ,「障害」はその領域を自然に拡大させていくことになる。
しかし本研究でも見てきた通り,「障害」は社会的に構成される。しかもインペアメントとディスアビリティの関係は,インペアメントが先にあり,ディスアビリティがそれに追随するというものでなければ,単にインペアメントとディスアビリティが併存するというものでもない。少なくとも本稿で論じてきた発達障害のケースにおいては,先にあるのはディスアビリティであり,インペアメントがそれに追随している。まず最初に,学習や行動面における課題が顕現化し,特別支援教育のリストに掲載されることで類型化され,「専門家」の診断でインペアメントと結びつけられて「障害者」がつくられる。
しかも本研究で見てきたように,発達障害のケースでは,二重の意味で障害は社会的につくられているといえる。一つは,障害の有無の判断基準が,インペアメントの次元にはなく,ディスアビリティの次元に帰属しているということである。発達障害の場合,中枢神経の機能の程度を客観的指標に基づいて計測することは不可能であるため,「障害/健常」を分かつ判断(診断)は,その個人の社会生活の逸脱の度合いやニーズの内容によって決められていくことになる。たとえそれが何らかの身体的要因に基づく現象であったとしても,それが障害となるか否かは,社会的場面における本人の様態で決められるということだ。よって,診断に主観が入りやすく,恣意的に陥りやすいという問題が生じる。
二つ目は,今述べたことの結果でもあるが,差別や不平等,家庭の不和など,全く異なる要因に基づく子どもの逸脱傾向をも,中枢神経の機能障害であるかのように読み込まれていく恐れが生じることである。先にも述べたように,学習面・行動面の課題は,中枢神経の機能障害や機能不全だけで生じるわけではなく,社会的・文化的・経済的・家庭的要因によっても生じる。ディスアビリティの次元で診断を行い,その後にインペアメントを「推定」するという方法は,このようなケースにおいては,問題の本質を捨象し,すべてを個人の身体的問題にお仕着せてしまう危険につながっている。
6 「教育的ニーズ」を最優先すべきだ
社会には差別や不平等が現前し,さらに階層間の格差は増大の一途をたどっている。一方,虐待やDVなど家庭内の問題も後を絶たない。子どもを育てるという観点からは,社会の状況はますます難しくなってきている。そういう社会状況を考えれば,私たち子どもに関わる仕事をしている者は言うに及ばず,すべての大人が,厳しい状況にある子どもたちをエンパワーしていくことが求められる。そういう子どもたちも「特別な支援」が必要な子どもたちなのだ。「インクルージョン教育」といったとき,少なくともそのような志向性は共有されるはずである。
しかし,今,日本で進められている特別支援教育は,「インクルージョン教育」の方向性を打ち出していながらも,その実,社会的に厳しい状況にある子どもたちのことは視野には入っていない。対象を「障害者」に限定しているために,社会的に厳しい状況に置かれている課題のある子どもたちに,「特別な支援」を届かせるためには,彼ら/彼女らを何らかのインペアメントと結びつけ「障害者」に仕立て上げる操作が,知らず知らずのうちに行われていくことになる。これが本当の意味での支援とはほど遠いことは言うまでもない。社会的な問題を社会の構成員全員で共有し,共にその解決を目指してがんばっていこうという方向ではなく,その責任を,その社会的な問題で苦しんでいる当の子どもの個人的な「病理」にお仕着せてしまい,何事もなかったかのようにふるまおうとしているように筆者には映る。ここに大人の欺瞞が見え隠れしている,と思うのは筆者だけなのだろうか。
もしかしたら筆者に対しては,次のような反論があるかもしれない。「何事も段階を経て進んでいくものだ,筆者の求める段階は次の段階だ」。しかし,それは違うと思う。なぜならば今,まさに目の前で,社会的な課題がまるでオセロでもしているかのように,次々と「ある」のに「ない」ことにすり替えられていくからだ。一旦「ない」とされた問題を解決するために,この先,誰が,何のために立ち上がるというのか。
ではどうしたらいいのか。特別支援教育の対象を「障害者」に限定するのではなく,「特別な支援が必要な児童生徒」とするべきだ。つまり判断基準を「教育的ニーズ」に求めるのだ。原因が何であれ,「教育的ニーズ」があれば特別支援教育の対象として位置づける。そしてその要因の特定は,後からやる。課題を解決するためには要因を特定することは重要なことだ。だから必ず要因の特定はしなくてはならないのだが,それを特別支援教育の対象にするかどうかの判断基準にしてはならない。
引用文献
- 原田琢也 2007,『アイデンティティと学力に関する研究-「学力大合唱」の時代に向けて,同和教育の現場から』批評社
- 石川憲彦・高岡健 2006,『心の病いはこうしてつくられる』批評社
- 文部科学省 2004,『小中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)』
- 文部科学省 2007,「特別支援教育の推進について(通知)」http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.htm
- 鍋島祥郎 1997,「あたりまえとしての学力保障」『シリーズ解放教育の争点1 解放教育のアイデンティティ』解放出版社
- Peter Mittler 2000,Working Towards Inclusive Education,David Fulton Publishers Ltd. (=山口薫訳 2002,『インクルージョン教育への道』東京大学出版会)
- 志水宏吉 2002,「学力低下の実態と克服の道すじ-2001年東大グループ調査からの報告」解放教育研究所編『解放教育』420号,明治図書,pp.9-30
- 高岡健 2007,『やさしい発達障害論』批評社
- 外川正明 2002,『教育不平等-同和教育から問う「教育改革」』解放出版社
- 特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議 2003,「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/018/toushin/030301.htm
- 特別支援教育士資格認定協会 2007,『特別支援教育の理論と実践Ⅰ概論・アセスメント』金剛出版
- 山口薫 1998,「インクルージョン」『リハビリテーション研究』第94号,(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
Copyright© 執筆者,大阪教育法研究会